
新しい施工プロセスへの挑戦
~イノベーションハブ本館建築プロジェクト
PROLOGUE
建設業界を取り巻く環境が大きく変化する中、新菱冷熱ではさらなる生産性向上に向けて、現場のあり方を見直し、施工プロセスを変革する取り組みを行ってきた。今回、当社の技術開発を長年担ってきた中央研究所を「イノベーションハブ」に改称して、本館を建て替えるにあたり、新たな施工方法や技術を導入した。これは、これからの新たな施工のカタチをつくる挑戦でもある。新菱冷熱のDX推進を担うデジタルトランスフォーメーション推進本部のリーダーY.S.が、この挑戦を語った。


Y.S.
デジタルトランスフォーメーション推進本部副本部長
兼 デジタル推進企画部長
1993年入社
工学部 化学工学科卒
入社後、施工管理担当として、新築・改修合わせて4件ほどの現場業務を経験した。その後、設計部門で半導体工場など主に産業系の案件を担当。その後、施工プロセス変革を担う社内プロジェクト「SHIPS (SHINRYO High Innovative Product System, シップス)」に参加。2022年10月には、SHIPSプロジェクトを大きく発展させるために発足したデジタルトランスフォーメーション推進本部に就任。新菱冷熱のDX推進を担うリーダーとして活躍する。
CHAPTER 01
新菱冷熱は、新しい技術や考え方の導入に積極的なこともあり、施工現場の改善には早くから取り組みを行ってきました。それが業務改革・施工プロセス変革の社内プロジェクトである「SHIPS」です。
施工現場の課題は様々ですが、最も大きな点は「現場に施工工程のあらゆる業務が集中する」ことです。業務が集中することで現場の働き方がハードになってしまいがちで、また品質の最終責任を担うプレッシャーも大きくなります。こうした環境を改善すること、つまり「現場を楽にする」ことが、魅力ある現場をつくり、現場で活躍したいという人を増やし、施工品質向上にもつながる。必須テーマだと考えています。
「SHIPS」を通じてこうした課題に取り組んでいる中、2022年10月にはデジタルトランスフォーメーション推進本部が発足し、私はその部署を担う立場になり、デジタル技術を活用して「SHIPS」をさらに大きく発展させ、施工プロセスを変革し現場を変えていく取り組みを進めることになりました。
私たちが施工プロセス改革のためにまず取り組んだのが「BIM(Building Information Modeling)」の導入です。これは、デジタルで作成した3次元の建物形状情報に加え、各室の名称や面積・材料・部材の仕様や性能、仕上げなどの属性情報を併せ持つ建物情報モデルです。設計での活用はもちろんですが、企画・設計から施工・メンテンナンスなどの維持管理フェーズまでを一元管理することができるのが特徴で、施工プロセスの効率化・生産性・品質の向上が実現できるものです。
当社は業界の中でも先駆けてBIMを導入し、設計から施工・維持管理のプロセスにおいて活用を進めてきました。ただ、BIMを活用するのは設計フェーズのみに留まるケースもあり、まだまだ活用を推進する余地があるのも現状です。私たちの部署はBIMデータ連携の基盤づくりをミッションの一つとしています。設計から施工へ、BIMデータをどのように連携させ効果的に活用していくか、BIMの可能性を最大限に引き出すことに挑み、現場の改善につなげていきたいと考えています。


CHAPTER 02
施工プロセスの変革は、設計・施工工程へのBIM導入だけでは完結しません。これまでの現場は、施工管理担当が自身の経験をもとに業務を進めるやり方が中心でした。そのため、施工プロセスが属人的になり、担当者のスキルや経験に拠ってしまう傾向がありました。また、現場単位で仕事を進める形は、ノウハウの蓄積や共有がしづらく、業務の標準化につながりづらいという課題もあります。
そのため私たちは、施工プロセスを「個から組織へ」というスローガンのもと、「2030年に目指すべき現場の姿」という現場の将来像を描きました。それは、現場に業務を集中させるのではなく、「現場」「バックオフィス」「オフサイト※」の3つの拠点に業務を分散し、それぞれが相互連携する、新しい施工のカタチです。
バックオフィスが施工計画やコスト管理、資機材や作業員の手配などを担当し、オフサイト拠点が現場の進捗に合わせた設備の加工・組立やユニット化を担当すれば、現場は品質・工程・安全の管理といったコア業務に専念でき、業務負荷を軽くできると考えています。
そして現場、バックオフィス、オフサイトをつなぎ、相互連携を実現する基盤となるのがまさにBIMとなります。
※オフサイト:現場から離れた場所という意味。従来は施工現場(オンサイト)ですべての工程を担っていたが、現場外の工場(オフサイト)で設備の加工・組立を行うという考え方。
BIMでつなぐために重要となるのが、データの利活用です。当社にはこれまで国内外の多くの現場で蓄積してきた様々なデータがあります。私たちが目指すのは、そのデータに基づいて施工の方向性を決定する、いわば「データドリブン施工」です。
そのためには蓄積されたデータを精査して質を向上させることが重要です。このビッグデータを、AIを活用しながら施工に利用すれば、現場の効率化・生産性向上につなげられますし、現場の働き方にも良い変化を起こせると考えています。
また、データをデータベース化し、現場運営のツールとしても活用したいと考えています。現場担当のノウハウをデータによって共有・標準化できれば、たとえ経験が浅い担当者であっても、経験豊富な担当者と同様の高品質な施工が可能となり、若い社員がもっと働きやすく、活躍できるようになるはずです。
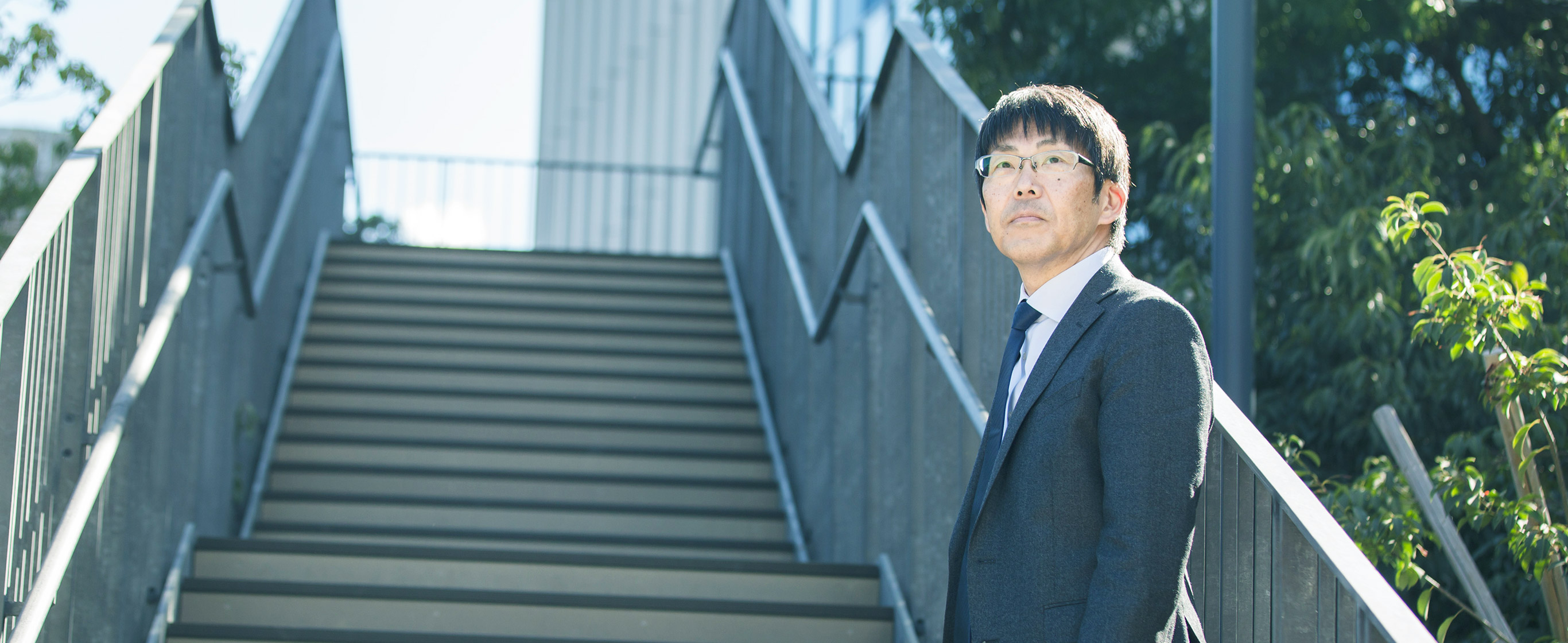
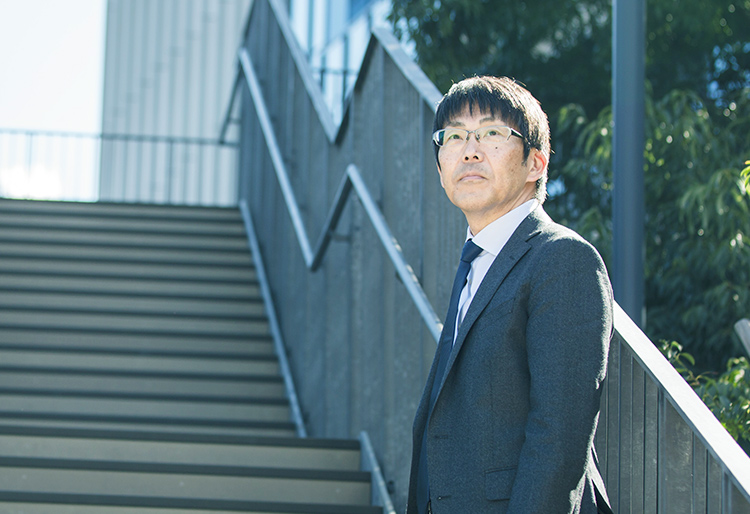
CHAPTER 03
2023年11月、茨城県つくば市にイノベーションハブ本館が竣工しました。新菱冷熱は、1970年に空調設備業界初となる技術研究所を開設し、その後、中央研究所と改組し、様々な技術開発を行ってきました。そして、急激に変化する社会の中にあっても新しい価値を創出し続けるプラットフォームとなることを目指し、その実現にむけて中央研究所再構築プロジェクトが立ち上がり、中央研究所は「イノベーションハブ」へ改称、本館の建設が始まりました。
私は、中央研究所再構築プロジェクトが始まった初期からメンバーとして参画し、計画づくりや建物のコンセプト立案に関わってきました。建設概要が固まってからは、このイノベーションハブの本館建設プロジェクトを、新しい施工プロセスの実験の場としても活用することとしました。これまで検討してきたBIMの本格的な活用、現場・バックオフィス・オフサイトの3拠点を相互連携する施工を、この現場で実践し、その成果や課題を収集する試みです。これは、この先、他の施工現場にも導入可能かを模索する試みでもありました。
イノベーションハブ本館建設の構想は「SHIPS」プロジェクトの頃から検討を進め、着工したのは2022年10月。私がデジタルトランスフォーメーション推進本部に所属したのと同時期に施工がスタートしました。
私たちがまず決めたのは、「フルBIM」で取り組むということ。これまでもBIMは設計等で活用してきましたが、設計・施工・維持管理にわたり、フル(full)でBIMを活用するのは初めての挑戦でした。
また現場では、現場でしかできないことのみを担当させ、それ以外の工程はバックオフィスとオフサイトを最大限活用することにもチャレンジしました。担当部署とも相談し、現場の担当者は、人数を絞ること、若手で比較的経験の浅い技術者とすることとし、現場代理人と施工担当者には若手女性社員2名が抜擢されました。延べ4,800㎡におよぶイノベーションハブ本館の建設現場。この規模であれば、通常なら現場には4、5名の担当者がいるのですが、人数を絞り、バックオフィスやオフサイトに業務を任せることが当たり前の環境をつくろうと考えたのです。また、比較的経験が浅い2名であれば、これまでのやり方にとらわれず、新しい施工のカタチに柔軟に取り組んでもらえるとも考えました。当の2人からは、最初は不安しかなかったと言われてしまったのですが(苦笑)。


CHAPTER 04
このプロジェクトでは、施工現場とバックオフィスの連携も大きなテーマとして取り組みました。施工現場とバックオフィスは、クラウドプラットフォームで様々な情報、BIMデータなどを共有しました。これまで現場で対応していた業務を整理し、現場でなくてもできる施工計画や工程の作成、出来高管理、コスト管理、資機材発注、作業員の手配等については、すべてバックオフィスが担当することとしました。
その結果、従来の現場で行っていた業務の60%をバックオフィスで対応することができ、これまでとはまったく異なる施工プロセスを実現、現場の働き方を大きく変えることができました。もちろん初めての挑戦ですから、うまくいかなかったこともありました。課題として見えてきたのは、工程の進捗管理です。現場の人数は絞ることができましたが、バックオフィスの担当者は約20名と規模が大きくなったため、情報共有のタイミングが担当者ごとに異なり、現場での実際の動きとタイムラグが生じ、施工の進捗に影響が出る場面もありました。これはバックオフィス化を本格導入したからこそ見えた点で、今後の改善につなげていける材料だとプラスに捉えています。
もう一つのテーマであるオフサイトにも取り組みました。オフサイトは現場の生産性を劇的に向上させられる取り組みです。イノベーションハブ本館の施工では、配管やダクトなど設備部材の80%をオフサイト(工場)でユニットとして加工・組立ててから現場に搬入しました。オフサイトでユニット化すれば、現場では据え付け作業がメインとなるため工程を削減できますし、限られた人数で効率的に作業を進められるようになります。さらには作業者の安全性や作業環境の向上にもつなげることができます。
また、施工情報のスキャンや墨出しロボットの導入など、デジタル技術の活用にもトライし施工の自動化・省力化の成果も得ることができました。これらのトライアルは、成果や見出された課題も含めて、施工プロセス変革に向けた大きな一歩にすることができたと感じています。実際に施工を担当した現場担当者からは、「バックオフィスとの連携・協働で、現場が変わっていくことが実感できました。これから変わっていく現場が楽しみ。とてもいい経験になりました」と、最初に感じていた不安とは正反対の嬉しい言葉をもらえました。


CHAPTER 05
イノベーションハブ本館の施工を通じ、BIM・データ連携など、新しい施工のカタチを実現し、「施工プロセスを変えることはできる」という手応えを感じました。次の挑戦はこの成果を多くの施工現場に展開していくことです。
これは決して簡単な取り組みではありません。建設現場では、当社だけでなく多くの関係者が協力して建物を作っていくため、当社の施工プロセスの考え方を理解してもらう必要があるのです。そのために、私たちの取り組みを設備業界全体で共有し、新しい施工のカタチをスタンダードにしていくことが、リーディングカンパニーである私たちの役割だと考えています。
もちろん社内の意識改革も重要です。「施工現場は実際に変えられる」「変えることで現場に多くのメリットが生まれる」というカルチャーをもっと当たり前にしていくこと、BIMの活用や現場・バックオフィス・オフサイトの相互連携にチャレンジしたいという意識を当たり前にすること。これこそが施工プロセス変革を成功に導くために最も重要ではないでしょうか。
今後、建設業界に限らず、人手不足が大きな社会課題となることは間違いありません。そうした中、この仕事の魅力をもっと高めるためにも、新たな施工プロセスへの変革は極めて重要な取り組みです。
建設業は、ものづくりを通じてインフラを担う社会的使命の大きな業界で、そこで働くやりがいはとても大きく魅力にあふれています。それは私自身も実感してきました。ものづくりを、今後も楽しく、魅力的な場としていくために、私たちは今後も施工プロセスの変革・業務改革に取り組んでいきます。その取り組みにはきっと終わりはありません。
当社は社員同士のつながりが深いところが強みだと思っています。そんな仲間たちとともに、新菱冷熱の新たな施工のカタチをつくっていきたい。将来、「新菱冷熱が施工の現場を変えた」、そう評価されることを目指して、一歩一歩確実に変革の歩みを進めていきたいと思っています。


RECOMMENDED CONTENTS
ENTRY
ENTRY(MYPAGE)